製品Q&ALCD(液晶)関連
LCD(液晶)に関する様々なQ&Aをご紹介致します。
疑問を解決するのに役立つコンテンツをそれぞれ詳しくご紹介しておりますので、是非お役立てください。


液晶とは、「液」体と結「晶」の中間の有機化合物です。棒状又は板状の分子構造をもち、分子は同一方向に並ぶ性質をもっています。
液晶は、電極間に電界をつくる事により向きを変える性質をもち(誘電率異方性)、その性質を利用する事により表示パターンを制御します。液体の性質を持っているため、様々な表示パターンを自由にデザインする事ができます。
下記は、主な特長です。


| TN | STN | FSTN | DSTN | |
|---|---|---|---|---|
| Twisted Nematic | SuperTwisted Nematic | Film‐STN | Double-STN | |
| 構造 | ネマティック液晶を90度ねじったもの | ネマティック液晶を260度程度ねじったもの | STN液晶パネルに位相差フィルムを貼り干渉色を除いたもの | STN液晶パネルに全く逆方向にねじった補正用のSTN液晶パネルを重ねる事で干渉色を除いたもの |
| 色 | 白/黒、灰色 | 黄緑、青 | 白/黒、灰色 | 白/黒、灰色 |
| 特長 | ・低消費電力 ・安価 |
・大容量表示が可能 ・高コントラスト ・視野角が広い |
※STNと同じ ・色が白/黒に近くなるためバックライトの色が反映し易い。 ・DSTNよりも透過率が良い。 |
※STNと同じ ・色が白/黒に近くなるためバックライトの色が反映し易い。 |
| 欠点 | ・視野角が狭い ・視野方向が偏り易い ・コントラストが低い ・大画面に不向き |
・色が付く ・ねじれ分応答速度が落ちる |
・ねじれ分応答速度が落ちる ・位相差フィルム分割高 |
・ねじれ分応答速度が落ちる ・補正用のガラス分割高 |
| Duty値 | Static〜1/16 | Static〜1/240 | Static〜1/240 | Static〜1/240 |
| コントラスト比 | 約3〜5 | 約3〜4 | 約2.5〜4 | 約2.5〜4 |


| 反射型 | 液晶パネルの背面に反射板を貼り、外来光のみにて使用するタイプです。バックライトは使わないで、外来光の反射光を利用します。 消費電力低くなりますので電池駆動に適しております。但し、バックライトがついていない(使用できない)ため、明るいところでのみしか使用できません。 |
|---|---|
| 半透過型 | 液晶パネルの背面に半透過反射板を貼るタイプです。外来光の反射光だけではなく、バックライトにても表示する事が可能となります。 使用環境が明るいところではバックライトをOffにし、外来光で使用致します。暗い場所ではバックライトの光を利用して使用致します。暗い場所と明るい場所両方にて使用可能のため好まれます。厳密に高輝度をお求めでない場合は、こちらの半透過タイプをお奨め致します。 |
| 透過型 | 透過偏光板を使用したタイプです。外来光は通り抜けてしまうため、バックライトを常時点灯して使用する必要があります。半透過タイプより光の透過率は高いため、ディスプレイの表面輝度は高くなります。 一方、日中太陽光下にて使用する場合、バックライトよりも太陽光の方がはるかに強いため、バックライトの光が負けてしまいます。結果的に全く見えなくなってしまうため、太陽光下で使用するには適しておりません。良い例が携帯電話です。 |


根本的には、液晶の配列と偏光板の組み合わせから生じる違いです。
- ポジティブタイプ
- 表示部分が黒くなり、背景の部分は透過のまま(つまり黒くならない)のタイプ。
通常は光が通過しており、背景は明るいままですが、文字の部分の液晶が反転し、光が遮断される事により、その部分のみが黒くなる。 - ネガティブタイプ
- 表示部分が明るくなり(つまり光が通っている透過状態)、背景が明るくならない(黒いままの)タイプ。
通常は光を遮断しているため、背景は暗いままですが、電気を流し文字の部分の液晶が反転する事で、その部分のみ光が通過し明るくなります。ちなみに、通常いわれる『STNブルー』と呼ばれる表示モードは、『STNイエローグリーンのネガティブタイプ』を意味しています。



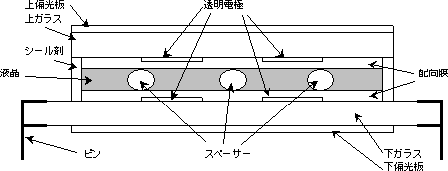


- COB
 Chip On Board
Chip On Board
LCD用LSIのベアチップをPCBにワイヤーボンディングし、樹脂コーティングしたもの。
特長は、PCBにビス穴が付いているため本体である筐体にビスにて取り付けがし易い。- COG
 Chip On Glass
Chip On Glass
LCD用LSIのベアチップを液晶用パネル(ガラス)に直に実装したもの。
特長は、PCB基板が不要になるためコストが削減し易すく、主に大量生産向け。但し、大容量若しくは大型の液晶モジュールには技術的な制約が出易い。薄型。- TCP(TAB)
 Tape Carrier Package
Tape Carrier Package
(Tape Automated Bonding)
LCD用LSIのベアチップをテープ上に搭載したもの。
COG同様薄型になるがCOGでは難しい大容量若しくは大型の液晶モジュールにする事が可能。- COF
 Chip on Film
Chip on Film
LCD用LSIのベアチップを、フィルム上に搭載したもの。
TABに似ているがTABで使用しているテープよりも薄いフィルムを使用。
ICチップ以外の電子デバイスを搭載する事が可能。(例えば、コンデンサなど)


そのような表記をした場合、下記のような解像度を意味します。
| 通称名 | 正式表記 | 解像度 |
|---|---|---|
| QVGA | Quarter Video Graphics Array | 320×240ドット |
| VGA | Video Graphics Array | 640×480ドット |
| SVGA | Super Video Graphics Array | 800×600ドット |
| WVGA | Wide eXtended Graphics Array | 852×480ドット |
| XGA | eXtended Graphics Array | 1,024×768ドット |
| SXGA | Super eXtended Graphics Array | 1,280×960ドット |
| WXGA | Wide eXtended Graphics Array | 1,366×768ドット |
| UXGA | Ultra eXtended Graphics Array | 1,600×1,200ドット |


LCDは自発光型のディスプレーではないので、透過型の場合、バックライトで背面からLCDを照明しなければなりません。
バックライトにはエッジライト方式(サイドから導光板に光を照射する方式)と直下型方式があります。小型のカラー/モノクロ液晶、ノート型パソコンおよびLCDモニターにはエッジライト方式が多く、液晶テレビには直下型方式が主に採用されています。
エッジライト方式の導光板は日本で開発されましたが、この技術を利用して海外メーカも含めて製品に搭載しています。キャラクタ液晶ディスプレイが開発された当初、直下型のLEDバックライトが主流でしたが、エッジライト方式が開発され、カラーLCDに採用されて来ています。
近年、表示面積の大きい液晶テレビ用バックライトは直下型が主流となっています。中小型LCDはエッジライト方式、直下型方式は大型TVのようなLCDに採用されています。
弊社の扱っている1.8インチから15インチ程度のLCDには、エッジライト方式のLED B/Lが採用され、薄型化、低消費電力化を特長としています。


光源には以下の種類のものがあります。
- 電球
- 発光ダイオード (LED)
- エレクトロルミネセンスパネル (EL)
- 冷陰極管 (CCFL)
- 熱陰極 蛍光灯(HCFL)
現在、主に使用されているのは、発光ダイオード(LED)です。
LEDで白色表示を行う場合、青、緑、赤の光の3原色の光源が必要になります。
電球は反射型LCDのフロントライトような形態で時計などに使用されています。
エレクトロルミネセンスパネル (EL) は平面性を利用してより、均一なバックライトとして使用されています。
冷陰極管 (CCFL) は長年に渡り、主流でしたが、液晶テレビを含めて、その座を明渡すほど、LEDが注目されています。
過去、液晶テレビやPCのディスプレイの面積の大きい物では光源に冷陰極管を使用する例が大半でありましたが、大型の液晶ディスプレイを中心にLEDを光源として使用する方向性がさらに加速されることが予想されます。


| EL | LED(発光ダイオード) | CCFL(冷陰極管) | |
|---|---|---|---|
| 英語名 | Electro Luminescent | Light Emitted Diode | Cold Cathode Fluorescent Lamps |
| 寿命(hr) | 約5,000 | 約50,000〜100,000 | 約15,000 |
| 厚み | 約1.0mm | 〇直下タイプ 約4.0〜5.0mm 〇サイド照光タイプ 約1.0〜3.0mm |
〇直下タイプ 約12.0mm 〇サイド照光タイプ 約3.0mm |
| 色 | 白、青、青緑、緑 | 黄緑、白、黄色、赤、アンバー | 白 |
| 特長 | ・薄型 ・色ムラがなく均等 |
長寿命 ・キャラクタタイプの殆どは、LEDバックライトを使用。 |
・高輝度 ・色むらがなく均等 |
| 欠点 | ・DC-ACインバータが必要 ・短寿命 ・発熱 ・大型には不向き |
大型には不向き LEDチップにより輝度のばらつきがあった場合色むらが出易い。 |
小型には不向き DC-ACインバータが必要 |
| その他 | ・直下タイプ: 高輝度、コストは割高(チップ数が多くなるため) ・サイド照光タイプ: 薄型、小型モジュール用 |
※各数値は、メーカー等によっても違いますのであくまで目安です。ご了承ください。


| パッシブ駆動方式(TN, STN, FSTN) | アクティブ駆動方式(TFT) | |
|---|---|---|
| 構造 | X電極(Segment端)とY電極(Common端子)を縦横の格子状に並べる。 | 各X、Y、対抗電極の3端子間に半導体(トランジスタ)を挟みスイッチイングさせる。 |
| 特長 | ・構造が単純 ・安価 |
・高Duty(=セグメント数が多い)場合でも高コントラスト及び高画質 ・応答速度に優れる。動画表示も可能。 |
| 課題 | ・配線(=セグメント数)が増えると画質が低下する。 ・応答速度が遅い。静止画向き |
・コストが高い。 |
| 主な用途 | 計算機、ワープロ、玩具、電子手帳、時計など | PC、TVなど |


スタティック駆動とダイナミック駆動(時分割駆動)に分かれます。
- スタティック駆動
-
最も基本的且つ理想的な駆動方法で、表示効果(コントラストや視野角度)が最も良好となります。これは各セグメントを、独立した1液晶駆動回路(nSEG×COM1)にて駆動させます。
例えば、4桁の7セグ数字表示をスタティック駆動にて駆動させる場合、セグメント数が28セグメントあるため、29端子(=28SEG端子+1COM端子)必要となります。この方法が最も理想的である反面、欠点もあります。各セグメントずつに駆動回路(つまりITO透明電極の配線)を設ける必要があるため、ドットマトリックスの様に、表示セグメントの数が多いディスプレイには適しておりません。配線が煩雑になり、外部端子の数が多くなり過ぎてしまうためです。
例えば、128×64ドットのグラフィック表示をスタティック駆動した場合は、表示セグメント数は8,192ドット(=横128ドット×縦64ドット)となり、8,193端子(=8,192SEG端子+1COM端子)必要となります。このような数量になりますと作るのはほぼ不可能です。その欠点を補うため、セグメント数が多いものに対しましてはダイナミック駆動にて駆動させます。
- ダイナミック駆動
-
ダイナミック駆動とは、COM端子を増やす事で表示を時分割(Duty=1/COM端子数)する方法です。簡単に言いますと、COMという「ページ」を増やすことになります。ドットマトリックス表示の場合は、ほぼ間違いなくダイナミック駆動を行っています。
例えば2枚の紙があり、1ページ目に海の場景が描かれており、2ページ目に上空を飛んでいるかもめの姿のみが描かれているとします。この2つの景色は別々のページに描かれていますが、その2枚を目にも止まらぬ速さで交互に瞬間で見た場合、あたかも海の上空をかもめが飛んでいる様に見える様になります。ダイナミック駆動とは、このような『高速なパラパラ漫画』のようなものです。グラフィックタイプ液晶の場合、通常『縦のドット数=コモン端子数』となります。
例えば128×64ドットの液晶では、縦列のドット数は64個ですのでCOM端子数は64本となります。上記のように、スタティック駆動では、端子数の合計が8,193端子となってしまいますが、COM数を64本に増やすと、合計端子数は192本(=128SEG端子+64COM端子)に減らす事が可能となります。配線の煩雑さを解消でき、高解像度表示にも対応できる様になります。
尚、時分割した場合の表示の仕方はDutyを用います。コモン数が64本だった場合、つまり64時分割したことになりますので、『1/64Duty』となります。(ちなみに、スタティック駆動の場合は、1/1となります。)ダイナミック駆動にも、長所のみではなく欠点があります。大きくは下記のような欠点があります。
- 応答速度が遅くなる。(「パラパラめくるページ数」が増えるため)
- 視野角度が狭くなる。
- クロストークが起こりやすくなる。
(※クロストーク = 選択のセグメントと非選択のセグメント間のコントラスト比が悪い現象。非選択セグメントも黒っぽくなってしまう現象。) - コントラストが落ちる。
- コントラストの低下を補うため、電圧を上げる必要がある。(=消費電力が増す。)
- TN液晶では高Dutyの表示はできない。通常1/16Dutyまで(製造メーカーにもよります。)。
1/16Duty以上となりますと、HTN液晶かSTN液晶となります。


- 液晶コントローラ
- 液晶パネルに表示する画像の信号処理を行います。
マイコンと液晶ドライバの仲介に位置し、両者のインターフェイスを受け持ちます。どのような表示にするかマイコンから受けた情報信号を、液晶ドライバ向けの信号、例えば表示タイミング信号(表示シフトクロック信号やフレーム信号)や表示データ(シリアルかパラレルか)等に変換します。 - 液晶ドライバ
- 液晶コントローラを通してマイコンから送られてきた表示情報を、液晶パネルへ送り込む最終デバイスです。
液晶パネルの各表示セグメント/ドットに適切な電圧を与えるもので、液晶ドライバがないと液晶パネルは駆動しません。又もう1つの重要な仕事として、液晶の劣化を防ぐために液晶駆動用の波形(交流区系波)を作り液晶パネルへ送る役割があります。


- キャラクタタイプ用ドライバ
-
キャラクタタイプ液晶モジュールのドライバは、通常液晶ドライバと液晶コントローラ、及びキャラクタジェネレータ機能が、全て含まれております。キャラクタジェネレータはCGROM(キャラクタジェネレータROM)とCGRAM(キャラクタジェネレータRAM)が御座います。
CPUより表示するCGROMの文字コードを転送致します。液晶モジュール側の液晶コントローラでは、その文字コードより文字パターンを選択し、ディスプレイへと表示致します。
- グラフィックタイプ用 ドライバ
-
グラフィックタイプの液晶モジュールには、大きく分けて3タイプ御座います。
- 液晶ドライバのみしか付いていない場合
液晶コントローラを別途ご用意する必要があります。標準品ではこのタイプが多く、主にCOBタイプのモジュールでよく見られます。お客様にて使いなれた液晶コントローラを既にご用意されている場合や、周辺回路上に設けている場合があるためです。 - 別々のデバイスとして、液晶ドライバと液晶コントローラ両方付いている場合
COBの標準品としては少数派かもしれません。理由は上記によります。また比較的高価となってしまうのも、理由の一つです。ですが最近このタイプのCOBも増えて来ました。お客様サイドで液晶コントローラを別途探し出しご用意する手間が省けるためです。液晶メーカーの方で互換性が既に取れておりますので、あとはお客様サイドのCPUとの整合性を取るのみです。 - ワンチップに液晶ドライバと液晶コントローラの両機能が内蔵されている場合
最近このタイプが非常に増えてきております。COGタイプやTABタイプ、COFタイプのドライバです。モジュールを小型化できますし、周辺回路の簡素化及び部品点数の削減に寄与致します。多くの場合内部昇圧回路が内蔵されているため、ハンディ機器など電池駆動のアプリケーション向けに適しております。コストダウンが望まれる大量量産品向けに採用される場合が多いです。(部材供給の関係上、少量では製造するのが難しいからとも言えます。)
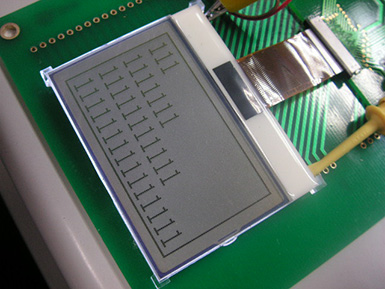 弊社標準品
弊社標準品
- 液晶ドライバのみしか付いていない場合
- セグメントタイプ用 ICチップ
-
セグメントタイプ用の液晶ドライバは、昨今お客様にてご用意頂く場合が殆どです。液晶ドライバ機能が内蔵されたマイコンが多く出てきたため、セグメント用液晶ドライバが市場から姿を消していっているためです。ですので、液晶メーカーでは、セグメントタイプの液晶モジュールを標準品としてはあまり扱っておりません。
例えばNECさんの78k/0SシリーズμPD789304ですと、セグメント信号は24本までコモン信号は4本まで1/4Dutyまで用意されております。つまり1/4Duty程度の比較的簡単なセグメント表示が可能です。
セグメント用液晶ドライバが少なくなっておりますが、市場から無くなった訳では御座いません。日本メーカーではRohmさんが標準ドライバとしてもっております。また台湾のホルテックHoltek社など海外メーカーも出てきております。弊社でも実際に、セグメント表示のLCDモジュールをカスタム作成したことが御座います。


通常納期は、ほぼ下記の通りです。
| 標準品 | サンプル品 | 約1ヶ月〜1.5ヶ月 |
|---|---|---|
| 量産品 | 約2ヶ月〜2.5ヶ月 | |
| カスタム品 | 図面 | 1週間〜10日 |
| ESサンプル品 | 図面ご承認後約1ヶ月少々 | |
| 量産品 | 約2ヶ月〜2.5ヶ月 |
※部材の市況により延びる場合もありますので、詳細は都度お問い合わせください。


液晶が劣化し寿命が短くなる原因は、主に下記の内容が当てはまります。
液晶が劣化した場合、現象の1つとして例えばコントラストが低下し、徐々に消費電流が増えていきます。劣化は突然起こるのではなく、徐々にその症状が顕れて来ます。
- 直流にて駆動させた場合
液晶は交流にて駆動させる必要があります。(液晶ドライバからの信号は交流区形波です。) - 規格外の温度範囲にて使用/放置していた場合
- 直射日光下での長時間の使用
液晶は紫外線に弱いため劣化していきます。 - 湿度の高い場所
- 静電気の多いところ
液晶モジュールのドライバに悪影響を及ぼします。


標準液晶モジュールが、残念にもメーカー側にて廃版の決定を下してしまう場合、大きく分けて2通りの理由が考えられます。
- 不人気
人気がなく、採算に合わない場合廃版にしてしまいます。 - IC等の部材が廃版となった場合
ICや他の部材が廃版になり完全に手に入らなくなった場合、それに伴い液晶モジュールも廃版にする場合があります。


基本的にはコネクタメーカに適合するコネクタの問合せをする必要があります。
通常多くのメーカが標準品をラインアップしていますので、特殊仕様でない限り、どこのメーカの製品でも使用可能です。
そのときにキーとなる項目は下記となります。
- TFTモジュールに使用されているFPC(Flexible Printed Circuit)のピッチを調べます。多くは、0.5mm〜1mmピッチとなっています。
信号用、LEDバックライト用、タッチパネル用といった3種類に分けられます。タッチパネル用についてはピッチが1mmとなっているものもあります。詳細は仕様書に添付されている図面を参照します。 - 適用FPC厚:0.3mm(公差±0.03mm)
- 極数、および導体の幅
- メッキの種類:通常のFPCは金メッキです。コネクタの端子メッキも金メッキ品を使用します。
- その他、上接点/下接点型、水平型/垂直型、高信頼性タイプなど、筐体、メインボードによって決まる仕様もあるかと思います。


タッチパネルは、金融機関のATM、自動販売機のような公共で使われるものから、コピー機、プリンタ、FAXなどのOA機器、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、携帯ゲーム機、などのデジタル機器を中心に使用されています。
こうした市場の状況から、弊社のTFT扱い製品にも小型のものを除いて、オプションとしてラインアップされています。
主として、抵抗膜方式の製品がラインアップされていますが、今後は静電容量式のタッチパネルのラインアップも充実して行く予定です。デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム機、コピー機、ファックス、カーナビなど、デジタル情報機器を中心に多方面での採用実績を目標にしています。


抵抗膜方式と静電容量方式を定性的に比較してみました。
製品にラインアップされているのは抵抗膜方式と投影型静電容量方式です。
| 抵抗膜 | 抵抗膜 (5線以上) |
表面型 静電容量 |
投影型 静電容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| タッチパネル透過率 | △/○ | ○ | ○ | ◎ | |
| タッチ反応 | 爪や棒 | ◎ | ◎ | × | × |
| 手袋 | ◎ | ◎ | △*1 | × | |
| 硬質プラスチック | ◎ | ◎ | × | × | |
| タッチ面 | 水滴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 面耐久性 | △ | △ | ○ | ◎ | |
| 手書き文字ペン入力 | ◎ | ◎ | △*1 | ||
| 外乱光影響 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| モワレ・縞・変色 | △ | △ | ○ | ○ | |
| 位置検出 | ◎ | ◎ | △ | ○ | |
*1専用ペンで対応可能


採用した液晶ディスプレイのメーカー、種類、そして利用環境によっても違いますが、一般には1万時間〜3万時間という寿命が一般的です。実際、液晶パネルが劣化するというよりは、「バックライト」が徐々に暗くなっていくことで輝度が下がり輝度が半減するのが寿命と定義されています。
輝度は半減しても、動作しなくなるというわけではなく、機能上は問題ありません。ユーザがどこまで使えるかということを判断するかがポイントです。
3万時間で考えますと、1日24時間継続して使用した場合、3万期間÷24時間÷365日≈3.4年、1日8時間使用する条件なら約10年は使用可能となります。さらに輝度を多少でも暗くして使用すればさらに寿命は長くなります。


アスペクト比とは画面の縦横の長さの比率を横対縦で示したものです。
広義にはある対象物について、X、Y、Z軸のうちの2つの軸における長さの比のことという定義がされています。
液晶ディスプレーの画面の比率を表す場合などにアスペクト比がよく使われます。
例えば、NTSC方式のテレビ画面は、横4に対して縦3の長さであり、アスペクト比は4対3となります。
ハイビジョン放送対応のHDTVが16対9、SXGAモニターが5対4などとなっています。
画素が正方形なディスプレーは、横と縦の画素数の比率がそのままアスペクト比になります。
弊社の扱っているTFT LCDも16対9、4対3などのアスペクト比の製品を多数、ラインアップしています。


すぐに使える装置組込用のオープンフレーム液晶モジュールをラインアップしています。
パソコンのアナログRGB信号のD-sub15コネクタと、NTSC/PAL信号のRCA(PIN)コネクタが装備されているので、いつものケーブルで接続できます。
サイズは5インチ〜12インチをラインアップしています。サンプル供給、および少量でも対応しますので、試作から、量産まで幅広く使用することができます。
タッチパネルのオプションにも対応し、USB、RS232Cなどのインターフェースを内蔵していますのでPCに直接接続してそのまま使用することが可能です。ドライバもCDで供給します。
抵抗膜型のタッチパネルはほぼ全機種についてオプションがあり、静電容量型についてもラインアップの拡充を進めています。


LVDSとは小振幅差動信号方式(Low-Voltage Differential Signaling)という名称で信号の電気的特性をあらわす用語です。
TIA/EIA(米国電気通信工業会/米国電子工業会)の汎用の(用途を特定しない)規格ANSI/TIA/EIA-644 (LVDS)として標準化されています。
LVDS規格では電気的特性を規定していてコネクタ形状やケーブルの特性やプロトコル(一例としてパラレルやシリアル信号で伝送することなど)を規定してはいません。
LVDSの特徴としては、
- 高速な信号の伝送が可能
- ノイズの発生が少ない
- 外来ノイズよる影響を受けにくい
- 消費電力が少ない
などがあげられます。弊社の取り扱いTFTモジュールにもLVDSが利用され始めています。
特に、高データレート、低電力消費、高耐ノイズ性、低ノイズ生成などの利点により、サイズの大きなLCDに今後も普及してゆくと考えられます。


有機ELディスプレイとは画面表示に有機ELという素材を使用するディスプレイです。
液晶、プラズマに次ぐ第三の薄型ディスプレイといわれることもあります。駆動方法からアクティブ型とパッシブ型に分類され、LCDと比較して、自発光型のディスプレーのため、輝度/コントラストが高い、視野角が広い、応答が速いなどの特長がありますが、LCDの大型化、低価格化などに押され、残念ながら普及が遅れている状況となっています。
携帯電話の画面など、小さい製品での利用にとどまっています。

